このページは移動しました。
3秒後にトップページへ移動します。
自動で切り替わらない場合は こちら をクリックしてください。

3秒後にトップページへ移動します。
自動で切り替わらない場合は こちら をクリックしてください。
안녕하세요^^ 크리스탈이에요
여러분은 식사할 때 어떻게 드시나요? 저는 일본생활이 오래돼서 숟가락의 사용이 많이 준것 같아요. 여러분은 한국 음식을 드실 때 숟가락과 젓가락 사용을 적절하게 하시나요?
(ヨロブン、食事する時、どのようにされていますか。私は日本での生活が長くスプーンの使用は非常に減ったような気がします。皆さんは韓国料理を召し上がる際、匙と箸を適切に使われているのでしょうか。)
今日は韓国料理を食べるには欠かせない「수저:スジョ(匙と箸)」の語源についてご紹介いたします!
「숟가락:スッガラッ=スプーン」の使用は古代からで、
日本、中国、韓国の3カ国で使っていたのですが、
それぞれの国の食習慣により、匙と箸の使用頻度は変化したと思います。
「숟가락:スッガラッ」の「숟」は、
鉄を意味する古語の「솓:ソッ」から由来していますが、
それは後に「술」にかわり、「술」+「가락」を合成語し、「술」は「숟」になります。
「술」から「숟」に変化するのは、
韓国語正書法29箇条には「ㄹ」で終わった言葉が別の言葉と合わさって合成語になる場合、「ㄹ」を「ㄷ」に表記する決まりがあるからです。
少し難しいですよね💦
「숟가락:スッガラッ」次に出現するのが
「젓가락:チョッガラッ=お箸」ですが、
「젓가락:チョッガラッ」の「저」は
漢字語の「箸:チョ」+「가락」が合わさった合成語です。
二つの言葉が合わさることによって「저」を発音しやすくするために
「저」の下に「ㅅ」のパッチムをつけています。
これを「사이시옷:サイシオッ」といいます。
古代は三国とも「숟가락:スッガラッ」使用から出発して今日は各国の食文化に合わせて「수저:スジョ(匙と箸)」の使用も変わっています。
日本は韓国ともっとも食文化が似ていますが、
一般的に食器は木製がほとんどですし、
ご飯も韓国より水分気が多いので、
「숟가락:スッガラッ」の使用よりは「젓가락:チョッガラッ」だけでも十分だったと思います!
それに対して韓国は米をスプーンで食べることも多いですよね。
何故かというと、ステンレス製品の食器で熱いため、
手で食器を持って食事するのが非常に難しく、
水分気の少ないご飯、汁気の多い食文化なので、
現在の「수저:スジョ(匙と箸)」を使うようになったでしょう。
ちなみに韓国は現在もステンレス製の箸がほとんどですが、
それは衛生のためです。
時代劇にもしばしば銀製の匙と箸の使用が見られますが、
それは「毒」成分に敏感に反応するので、
政権の争いが激しかった王様を守る一つ方法でもありました。
韓国の歴史にも大きく関わる「수저:スジョ(匙と箸)」について
理解できましたでしょうか?^^
うーん、まだ難しい!という方はぜひアーキヴォイスのレッスンで
詳しく解説いたします♪
<京都校体験レッスンはこちら>

<オンライン体験レッスンはこちら>
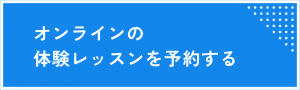
<メルマガご登録はこちら>
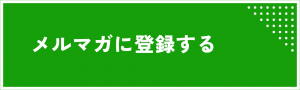
안녕하세요. 크리스탈이에요.
今日は名前や役職名、団体名などにつける敬称の「様」と「님」についてご紹介いたします。
日本にも古くから相手の名前などにつけて呼ぶ表現として「ちゃん」、「君」、「さん」、「様」、「殿」などがあります。
「ちゃん」はさんの音変化による呼び名として、「名前+ちゃん」や「おじいちゃん」のように親しみがこもったつけ方です。「君」は今や主に男の子につけて親しみや軽く敬意を表しますが、本来は中国から入ってきた言葉で君主に使われた表現です。次の「さん」は様の音変化によるもので人名、役職名、団体名などにつけて尊敬を表したり、動物名などにつけて親愛を表したり、または「ご苦労さん」のような使い方で丁寧の意を込めて使います。
最後に「様」と「殿」の表現ですが、今や人名などにつけていますが、本来は異なっていたようです。室町時代には「様」は人を指していい、「殿」はその人が住んでいる家屋敷を指したもので、ランク的にも「殿」より「様」のほうが格上だったようです。そのため、「様」の語源は、漠然と方向を示す「さ」+接尾「ま」がくっついたものとして、直接相手を指し示すのではなく、漠然とそちらの方向を示すことにより相手への非礼がないように配慮した言葉だと言われています。
さすが、相手への配慮を最優先に考える日本人の国民性が言葉にも表れていますね。
韓国にも日本の「―様」のつけ方として「님」、さんは「씨」や「양」、そのほかには「군」、「-아/야」などがあります。主に女性に使っていた漢字の嬢の音読み「양」や男の子に使っていた「군」(=君)は現在ほとんど使われず、さんづけとしては氏の音読みの「씨」のみです。同輩や目下の人に使う「名前+아/야」は親しみがこもった呼びかけとして~よ、~や、~ちゃんのニュアンスで用いられます。
敬称として様にあたる「님」はつけ方としては日本の様と同じですが、その語源はかなり違います。古代、韓国には太陽と大地、水などを支配していた神「니마」と女神「고마」がいたようで、「님」は、本来太陽神を意味する古語の「니마」から音変化した言葉です。そこから相手の呼びかけとしての「님」の意味は、相手を神のようにとても大切に尊敬をする意味合いがあるようです。
ちなみに「니마」はもう一つの「額」という意味があります。古語で額を「니마」と言ったのは人間の体で太陽を一番当たりやすい部位が額だからです。頭は髪で覆われているので直接太陽に当たらないと考えていたようです。この説は日本語の額=ひたいの単語からも容易に推察できます。日本の古代にも太陽神を崇拝していたし、太陽神を祭って祭祀を行っていた「ひたい」 (=日台)があったようです。その意味合いで日本でもおでこの意味である額の言葉が生まれているのではないかと考えているようです。